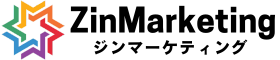質問の質を考える
何かを知りたいときに、誰かに聞いたりすることがありますが、
その質問の質って考えたことってありますか?
ふんわりした質問をすると全体的なふんわりした答えが、
細かく聞いたときはポイントを絞った答えが帰ってきます。
なので、自分はどのポイントを知りたいのか、具体的なことを知りたいのかなど、
知りたいことを知るために質問の質を考えてみましょう。
ーーーー
何かわからないことがあると、誰かに聞きますよね。
その質問の質で相手が答えられる内容、答えの深さがわかってくることって
意識していますか?
例えば、飲食店でめちゃめちゃ美味しい料理を食べたとします。
このとき、どんな質問をしますか?
「この料理美味しいね!これってどんな料理?」
と聞くのと、
「この料理ものすごく美味しいね。
特に、このトマトベースで作っているのにさっぱりした風味があるのだけど、
何か特別なスパイスを使っているの?それとも作り方に秘密があるの?
教えてほしいんだけど」
と聞くのでは、帰ってくる答えが違ってくるのがわかりますよね。
1つ目の方だと「これはチュニジア料理です」…(以上)
ってだけでしょうけど、(話し好きのウェイターなら違ってきそうですが(笑))
2つ目だと「これはチュニジア料理で、そこでしか取れない秘密のスパイスを使っていて・・・」
と具体的かつ多くの情報を得ることが出来ます。
この場合、ただの雑談ではなく、料理の内容を具体的に知りたいのであれば、
具体的に自分の知りたいポイントに絞って(もしくは導いて)質問をすることが必要なのです。
この話は、飲食店だけの話ではなく、ビジネスで広く活用できる考え方です。
1つ目のような聞き方をする人がとても多いのではないでしょうか?
クライアントに聞くとき、外注先に聞くとき、システム構築者に聞くときなどなど、
具体的にというより、相手が答えやすいように質問できているでしょうか?
このポイント、考えなくちゃいけないのは、質問内容の言語化です。
自分の得意な分野であれば、様々なことが言語化できています。
私の場合だと、CTAとはなに?とか、LPの流れとかは言語化できます。
でも、デザインの分野だと簡単にはいきません。
言語化できる・できないの違いは、基本的に知識量だと思っています。
専門的にやってきた、学んできたことは言語化できるけれど、
知識がないから、うまく言葉にできないってことになります。
このプロセスを一橋大学の野中郁次郎は「SECIモデル(SECIプロセス)」として、
ナレッジマネージメントの方法として著書を出しているので、
もし、詳しく知りたいと思うのでしたら読んでみてください。
学術的な話はこのぐらいにして、
ビジネスの場で役立つように、うまく使えるようにするのでしたら、
次の事を気をつけて置くだけで十分でしょう。
自分はどのポイントを知りたいのか、具体的なことを知りたいのかなど、
知りたいことを知るために質問の質を考える。
まずはこれをやっていきましょう。